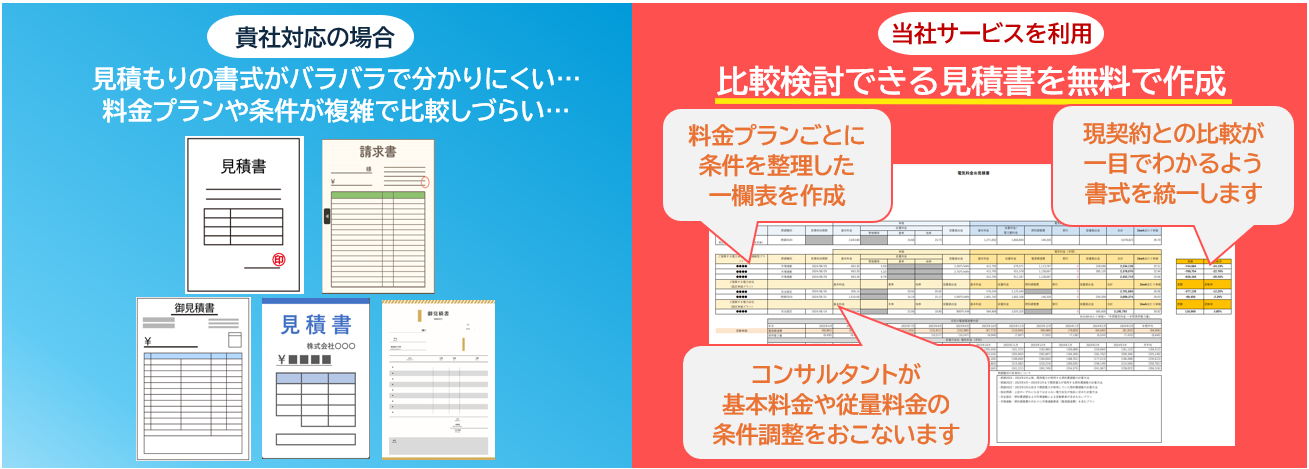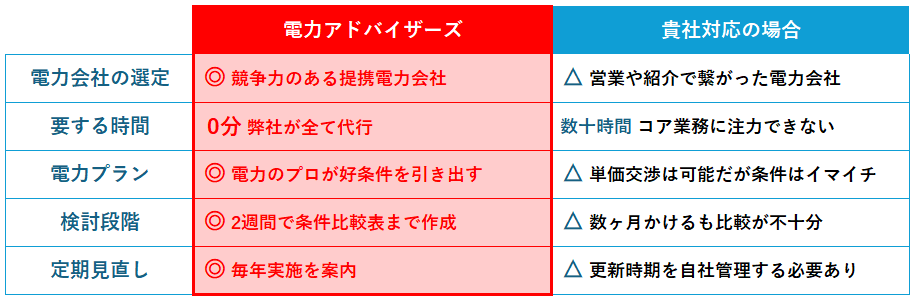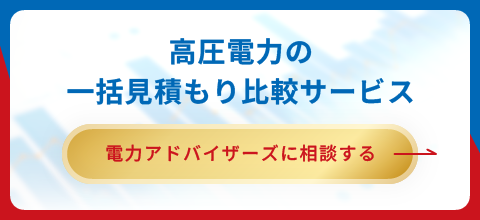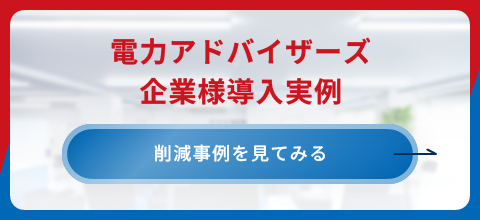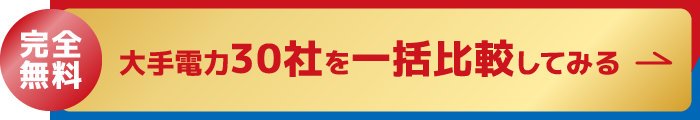契約電力とは?決め方と下げる方法を高圧向けにわかりやすく解説
の基本料金を下げる方法まとめ.jpg)
「契約電力を下げる方法を知りたい」
「基本料金がなぜこんなに高いのか分からない」
「節電しているのに、思ったほど電気代が下がらない」
このような悩みをお持ちではありませんか。
電気代を見直すうえで節電は重要ですが、現場に過度な我慢を強いると、業務効率や職場環境の悪化につながりかねません。
実は、電気代が下がらない原因が「節電不足」ではなく「契約電力」にあるケースは非常に多いのです。
この記事では、高圧・特別高圧契約を対象に、
- 契約電力とは何か
- 契約電力の決め方
- 契約電力を下げる具体的な方法
を、実務目線で分かりやすく解説します。
目次
契約電力とは?基本料金との関係を理解しよう
契約電力とは、電力会社との契約上で定められる「30分あたりの最大使用電力(kW)」のことです。
高圧・特別高圧の電気料金では、この契約電力をもとに基本料金が計算されます。
まずは、電気料金の全体構成を確認しましょう。
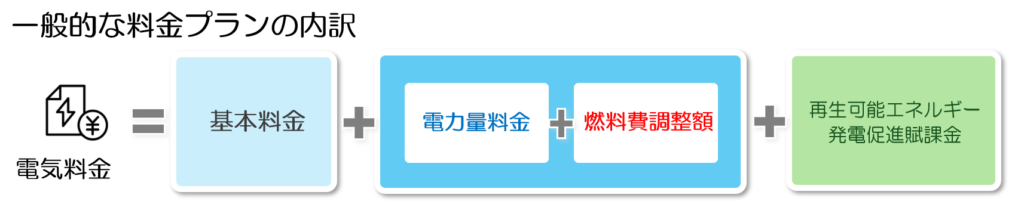
| 【高圧電力の電気料金の構成】
電気料金=基本料金+電力量料金+燃料費調整額+再生可能エネルギー賦課金 |
このうち、契約電力が直接影響するのが基本料金です。
基本料金の計算式は以下です。
| 【高圧電力の基本料金の計算式】
基本料金=基本料金単価(円)×契約電力(kW)×力率(%) |
上記計算式から読み取れるとおり、契約電力のkW数が高いほど、毎月の基本料金は高くなります。
関連記事:高圧電力の基本料金仕組みと計算方法|削減方法
関連記事:電気料金の力率割引をわかりやすく解説|計算式や改善方法もご紹介
関連記事:燃料費調整額とは|計算方法と今後の見通しをわかりやすく解説
関連記事:再エネ賦課金とは?仕組みや安くする方法をわかりやすく解説
|
※補足:低圧契約との違いについて 低圧(契約電力50kW未満)の場合、「契約電力」という考え方はなく、基本料金は契約容量(A・kVA)によって決まります。 本記事で解説している契約電力の仕組みは、高圧(50kW以上)および特別高圧契約が対象です。 |
契約電力の調べ方
契約電力は、毎月届く電気料金の明細書(検針票)で確認できます。
明細の中に「契約電力(kW)」として記載されています。
紙の明細が手元にない場合は、東京電力・関西電力など契約中の電力会社のマイページにログインし、Web明細から確認することも可能です。
契約電力の決め方|実量制と協議制の違い
契約電力の決め方は、契約区分によって異なります。
契約電力の決め方について、高圧小口(50~500kW)は「実量制」を、高圧大口と特別高圧は「協議制」を採用しています。
| 高圧 | 小口 | 50~500kW | 実量制 |
| 大口 | 500~2,000kW | 協議制 | |
| 特別高圧 | 2,000kW~ | ||
実量制(契約電力500kW未満)の決め方
高圧小口(50〜500kW)の場合、契約電力は「実量制」で決まります。
実量制とは、直近1か月の最大需要電力と、その前11か月の最大需要電力のうち、最も大きい値を契約電力とする方式です。
| 最大需要電力とは?
最大需要電力とは、30分ごとの平均使用電力のうち、月間で最も大きい値を指します。1日24時間を30分単位で区切ると48コマ、30日間の月であれば1,440コマになります。この1,440コマの中で、最も電力使用量が大きかった30分間の平均値が、その月の最大需要電力です。
|
たとえば、直近12か月の中で2月の最大需要電力が370kWだった場合、
その370kWが向こう1年間の契約電力として適用されます。
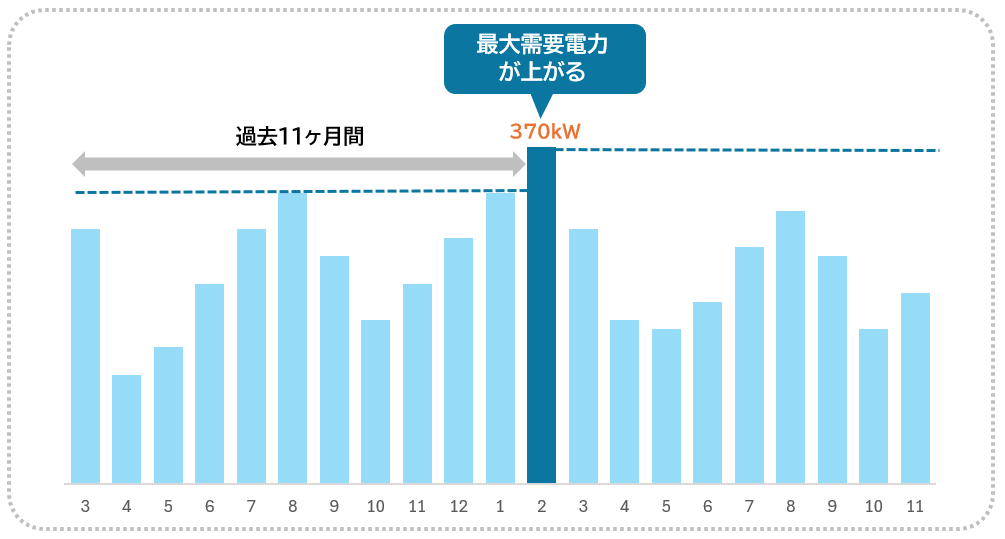
重要なのは、日々の使用量をどれだけ減らしても、30分単位のピークが変わらなければ契約電力は下がらないという点です。
協議制(契約電力500kW以上)の決め方
高圧大口・特別高圧では、協議制が採用されます。
協議制では、まず直近12か月の最大需要電力を算出したうえで、受電設備の内容、使用負荷、業種ごとの負荷率などを踏まえ、契約更新時に電力会社と協議して契約電力が決定されます。
なお、月ごとの最大需要電力が契約電力を超過した場合、割増料金や追加の基本料金が発生することがあり、注意が必要です。
契約電力を下げる方法|基本は「最大需要電力」を下げること
前述のとおり、契約電力は直近12か月間の最大需要電力によって決まります。
そのため、契約電力を下げるには、30分単位のピーク電力を抑えることが不可欠です。
ここで重要になる考え方が、ピークカットとピークシフトです。
ピークカット|ピーク時の電力使用量を抑える
ピークカットとは、電力使用量が最も多い時間帯のピークを直接下げる取り組みです。
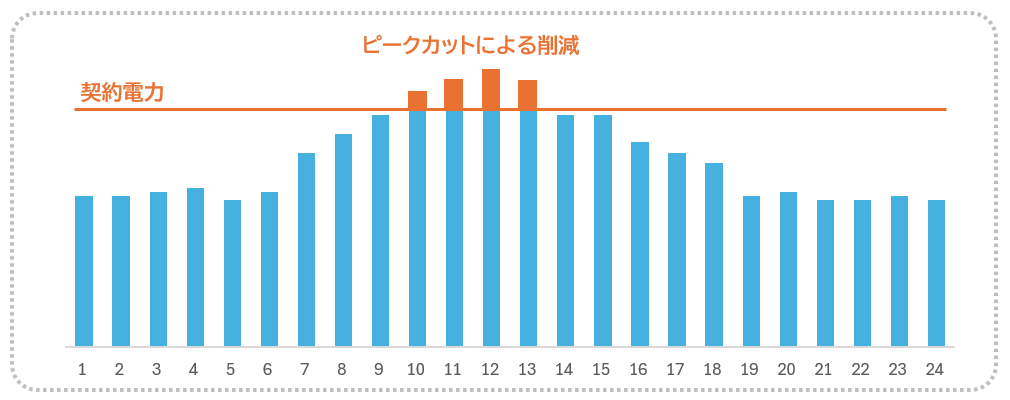
直近12か月の最大需要電力を抑えることができれば、翌年度の契約電力を下げることができ、基本料金の削減につながります。
契約電力が下がることによって、基本料金の削減につなげることができます。
東京電力のベーシックプラン(基本料金単価:2,530円00銭)を例として、契約電力が30kW下がった場合、月間で64,515円、年間では774,180円の削減効果が見込めます。
デマンドコントロールによるピークカット
では、実際にピークカットを実施するためには、どのような手段があるのでしょうか。
契約電力を下げるためによく使われる、代表的な装置はデマンドコントロールです。
デマンドコントロールとは、電気の使用量を可視化し、設定した値を超えないよう、警告をおこなったり、電気機器や設備の自動制御を行う装置のことです。
電力使用量を常時監視し、無駄な電力消費を抑えることで電気代削減につながります。
なお、デマンドコントロールには2つの方法があります。
- デマンドコントロールシステム
- デマンド監視装置
それぞれについて見ていきましょう。
デマンドコントロールシステムの特徴
デマンドコントロールシステムとは、あらかじめ設定した目標デマンド値を超えないように、空調設備や各種電気機器を自動で制御する装置です。
電力使用量が増えそうになると、エアコンの出力を弱めたり、一部の機器の電源を自動でオフにすることで、ピーク電力の発生を防ぎます。
最大のメリットは、電気機器の制御をすべて自動で行える点です。
人が操作する必要がないため、調整漏れや操作ミスが起こりにくく、安定したピークカット効果が期待できます。
また、電力使用量の計測や記録も自動で行われるため、使用状況を把握しやすい点も特徴です。
一方で、デメリットとしては、導入コストが比較的高いことと、職場環境に影響が出る可能性があることが挙げられます。
特に夏場などに空調が自動で制御されると、エアコンが急に弱まったり停止したりする場合があり、従業員の不満やストレスにつながることもあります。
デマンド監視装置の特徴
デマンド監視装置は、電力使用量が設定した目標デマンド値を超えそうになった際に、警報やメールなどで知らせてくれる装置です。
電気機器を自動で制御する機能はなく、通知を受けた人が手動で設備の使用を調整します。
メリットは、導入コストが比較的安い点です。
また、実際に人が調整を行うため、従業員一人ひとりが電力使用を意識するようになり、節電意識の向上につながるケースもあります。
一方で、操作を人に頼るため、対応が遅れたり、調整しきれなかったりすることがあります。
そのため、自動制御のシステムと比べると、ピーク抑制の精度や効率は劣る点がデメリットです。
ピークシフト|使用時間帯をずらして平準化する
ピークシフトとは、電力使用量の多い時間帯から、少ない時間帯へ使用を移すことで、最大需要電力を抑える方法です。
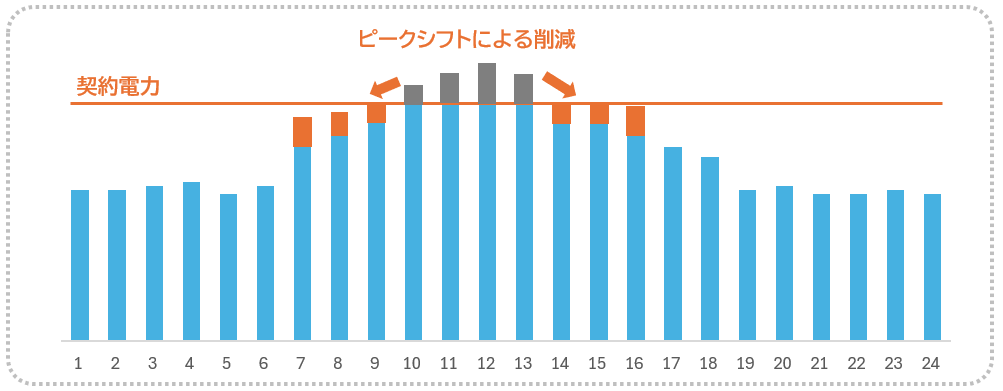
電気使用量が多い「山」の部分を、「谷」の部分に移動する取り組みのことです。
総使用量が変わらなくても、ピークを分散できれば契約電力の削減につながります。
ピークシフトには蓄電池の導入が有効
蓄電池とは、電気を一時的に蓄え、必要なタイミングで使えるようにする装置です。
電力使用量の少ない夜間や早朝に電気を充電し、使用量が増える昼間に放電して利用することで、電力会社から購入する電気を抑え、ピーク時の電力使用量を下げることができます。
この仕組みによって、ピークシフトを実現し、契約電力の削減につなげることが可能です。
実際には、工場設備の稼働時間を日中から夜間へ変更したり、出勤日を平日から土日・祝日に切り替えたりするのは、業務上の制約が多く、簡単ではありません。
そのため、ピークシフトに取り組む方法としては、運用を大きく変えずに対応できる蓄電池の導入が、現実的な選択肢になるケースもあります。
自治体によっては補助金制度が用意されている場合もあるため、検討の際にはあわせて確認してみるとよいでしょう。
無料で電気代の基本料金を見直す方法|電力会社の切り替え
ここまで、契約電力を下げる方法として、ピークカットやピークシフト、デマンドコントロール、蓄電池の活用などを解説してきました。
これらはいずれも有効な手段ですが、設備投資が必要になったり、運用ルールの変更が求められたりと、すぐに実行できないケースも少なくありません。
その点、電力会社の切り替えは、設備を購入することなく、初期費用もかけずに電気代を見直せる方法です。
特に高圧契約では、契約電力を変えなくても「基本料金単価」や「従量料金単価」を見直せる可能性があります。
基本料金単価を下げるだけで、固定費は確実に下がる
高圧電力の基本料金は、次の計算式で決まります。
基本料金 = 基本料金単価 × 契約電力(kW)× 力率
この式から分かるとおり、ピーク対策によって契約電力を下げなくても、基本料金単価そのものを下げれば、毎月の基本料金は確実に下がります。
たとえば、東京電力の高圧向けベーシックプランでは、基本料金単価は1kWあたり2,530円で設定されています。
仮に、契約電力が200kW、力率が100%の場合、基本料金だけで毎月43万円を超える固定費が発生します。
この契約条件のままでも、電力会社を切り替えて基本料金単価が下がれば、契約電力に手を加えずに電気代を削減することが可能です。
実際には、単価が数百円/kW変わるだけで、年間では数十万円から数百万円規模の差になるケースもあります。
従量料金も含めて見直せるのが、新電力の特徴
電力会社を切り替えるメリットは、基本料金単価だけではありません。
新電力の中には、法人向けに特化した料金設計を行っている会社もあり、電力量料金(従量料金)の単価まで含めて見直せる場合があります。
ピーク対策や省エネによって使用量を抑えても、単価自体が高ければ効果は限定的です。
その点、契約条件に合った電力会社を選ぶことで、「使用量 × 単価」の両面から電気代を最適化できる可能性があります。
また、設備投資による削減は、効果が出るまでに時間がかかることもありますが、電力会社の切り替えは、契約開始月から効果が表れやすい点も特徴です。
切り替えは無料だが、選び方を誤ると逆効果になることも
電力会社の切り替えは、多くの場合、工事不要で切り替え費用もかかりません。
そのため、「まずは電力会社を変えてみよう」と判断しやすい一方で、料金の安さだけで選んでしまうと、後からリスクが顕在化することもあります。
たとえば、
- 価格変動リスクの高いプランを選んでしまう
- 契約期間や解約条件を十分に確認していない
- 自社の使用実態に合わない料金設計を選んでしまう
といったケースでは、当初は安く見えても、結果的に不利になることがあります。
電力アドバイザーズでは、契約電力や電気の使い方を整理したうえで、複数の電力会社・料金プランを比較し、条件に合った選択肢を検討します。
単価だけでなく、契約条件やリスクも含めて判断することで、安心して電気代の見直しを進めることが可能です。
設備投資による対策を検討する前に、まずは無料で見直せる電力会社の切り替えから着手する。
それも、電気代削減を進めるうえでの、現実的で無理のない選択肢の一つと言えるでしょう。
関連記事:新電力とは?仕組み・メリット・デメリットをわかりやすく解説

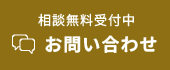
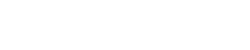
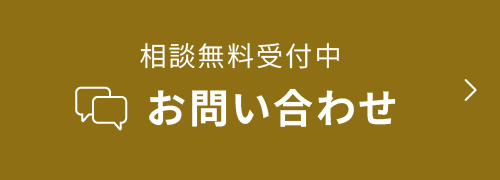
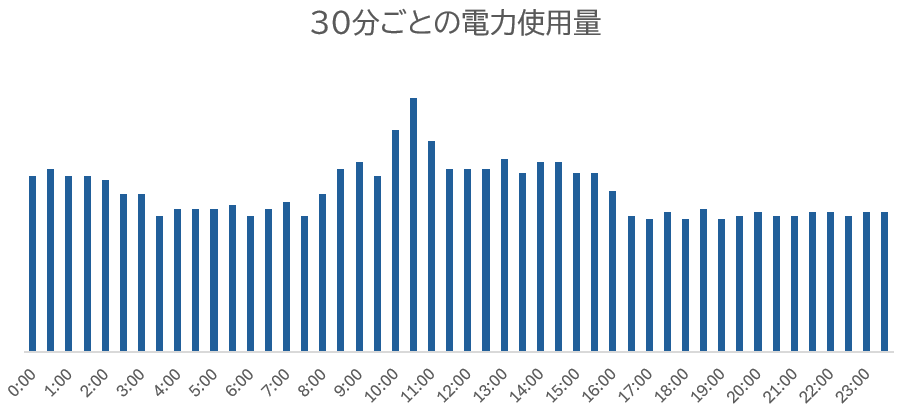

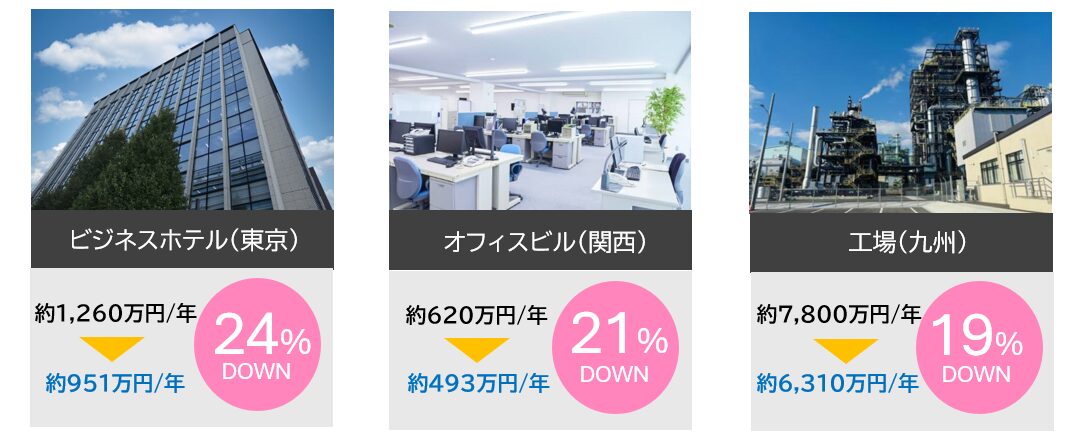

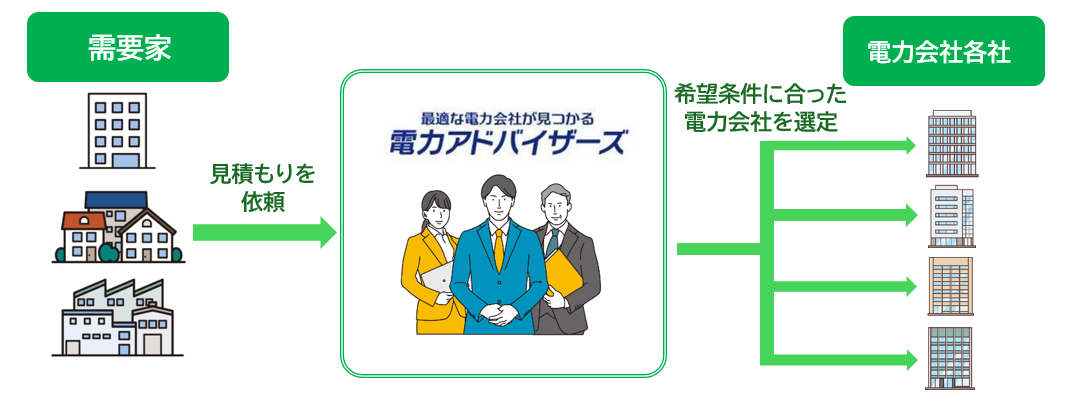 さらに、お客様へ電力会社から直接連絡が入ることはなく、煩わしいやり取りの手間も不要です。
さらに、お客様へ電力会社から直接連絡が入ることはなく、煩わしいやり取りの手間も不要です。